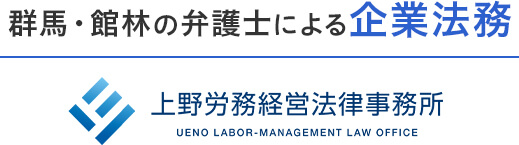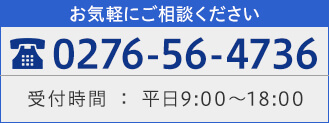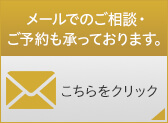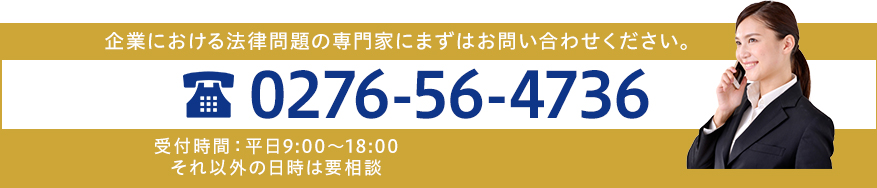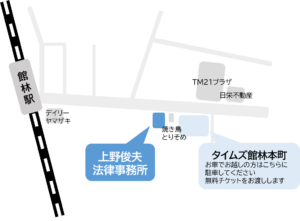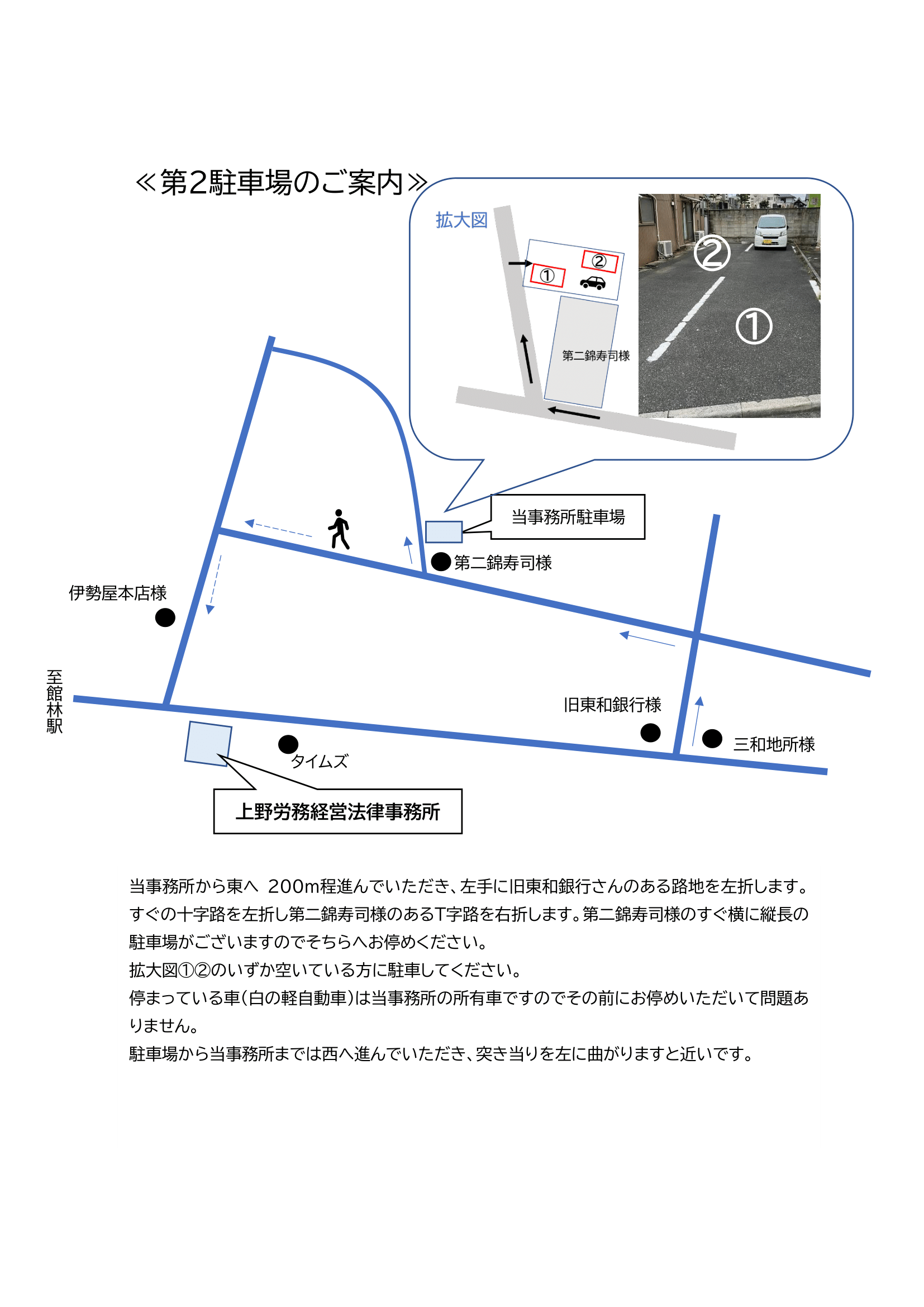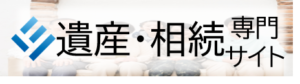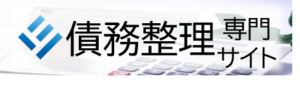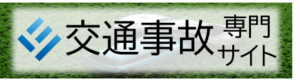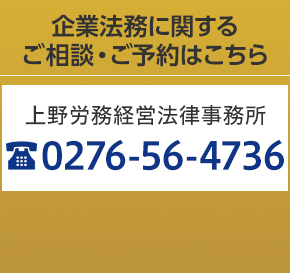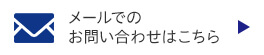「正社員採用」表示で無期雇用と認定された事例-マンダイディライト事件- 大津地判令和6年12月20日判決
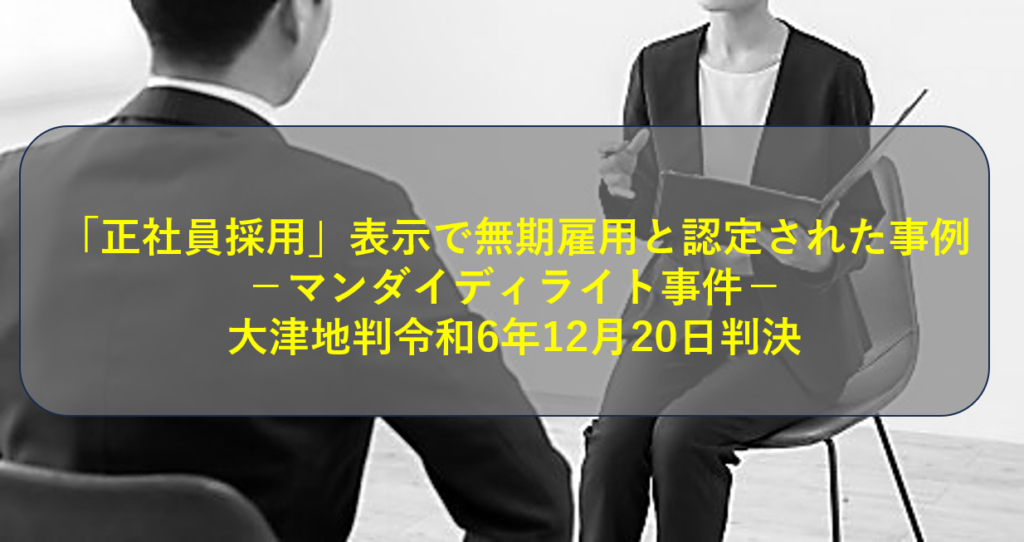

事件の概要
本件は、ハローワーク求人票に「正社員」「雇用期間の定めなし」と明記されていたにもかかわらず、実際には有期雇用と扱われ、2か月後に雇止めされた従業員が、無期労働契約の成立を主張して雇用継続を求めた事件です。
原告は、被告(人材派遣業を営む株式会社)のハローワーク求人票を見て応募し、令和5年7月から勤務を開始しました。求人票には、「正社員」「雇用期間の定めなし」「試用期間2か月」と明示されていました。しかし、会社側は実際には2か月間の有期雇用であるとし、契約書上も「更新なし」とされていました。
原告は、面接時にも契約書作成時にも、有期雇用であるという説明は受けておらず、就労開始後に突如として「雇止め」を通告され、翌9月以降の就労を拒否されました。そこで原告は,労働契約上の地位の確認と賃金の支払いを求めて提訴しました。

裁判所は、原告が求人票の記載を前提に応募し、会社から内定の通知を受け、就業を了承した経緯などを踏まえ、契約書作成以前の時点で既に「雇用期間の定めのない始期付労働契約」が成立していたと認定した上,原告と被告との間には現在も有効な無期雇用契約が存在するとし、被告に賃金の支払いを命じました。
判例のポイント
この判例で重要なのは、労働契約の成立時期とその内容が、後日取り交わされた「雇用契約書」の文言よりも、求人票や内定通知時点の内容によって判断された点です。裁判所は、求人票や面接時のやり取りなどを重視し、会社側が一方的に有期契約へと「書面で変更」した事実に対して厳しく判断しました。
判決では、次のようなポイントが示されています:
1.内定通知=労働契約の成立
就業開始日を明示して内定を通知し、原告がこれを承諾したことで、求人票に基づく無期の労働契約が成立したと判断されました。これは、「申込みと承諾」により契約が成立するという民法上の原則を適用したものです。
2.契約書は後からの「確認行為」
契約書に2か月の雇用期間が記載されていたものの、その前段階で成立していた契約内容を変更するには、労働者の自由意思に基づく合意が必要であるとされました。十分な説明がなく、労働者に一方的に署名させた事情がある以上、契約書による不利益変更は無効とされました。
3.求人票の記載の重み
求人票には「正社員」「雇用期間の定めなし」とあり、会社のウェブサイト上の情報もこれに整合していました。会社側が「記載ミス」と主張しても、それが外部に提示された情報であった以上、その内容に従った契約が成立したと判断されました。
本件は、採用活動において求人票の記載や内定通知の内容が法的拘束力を持つことを再確認させるものであり、人事実務において非常に示唆に富む判例といえます。
弁護士の視点:求人票と労働契約の不一致が招くリスク
求人票に記載された労働条件と、実際に締結される労働契約の内容が一致しないという問題は、労働トラブルにおいて頻繁に裁判で争点となります。
私の経験では、特に多いのが、求人票には固定残業代の記載がなかったにもかかわらず、実際には固定残業代が含まれる形で契約が結ばれ、退職した社員が「固定残業代は無効だ」として会社に残業代を請求してくるケースです。
中小企業においては、人手不足の深刻化に伴い、少しでも良い条件で求人を出したいという意向がある一方で、人件費抑制の観点から、求人票よりも低い条件で契約を結ぶといった実態が散見されます。会社側のこうした事情も理解できますが、本件のように、求人票の記載内容がそのまま契約内容として認定されてしまう可能性が高いことを認識しておく必要があります。
したがって、労務管理上のリスクを低減するためには、求人票の内容と実際の労働契約の内容を極力一致させることが極めて重要で、これにより将来的な紛争の発生を未然に防ぐことができます。