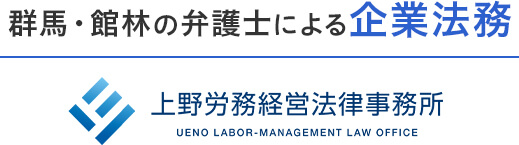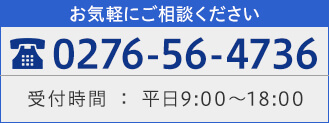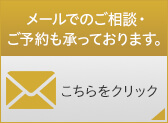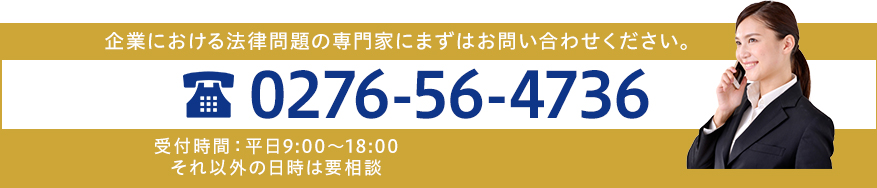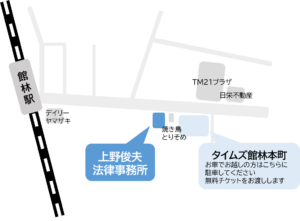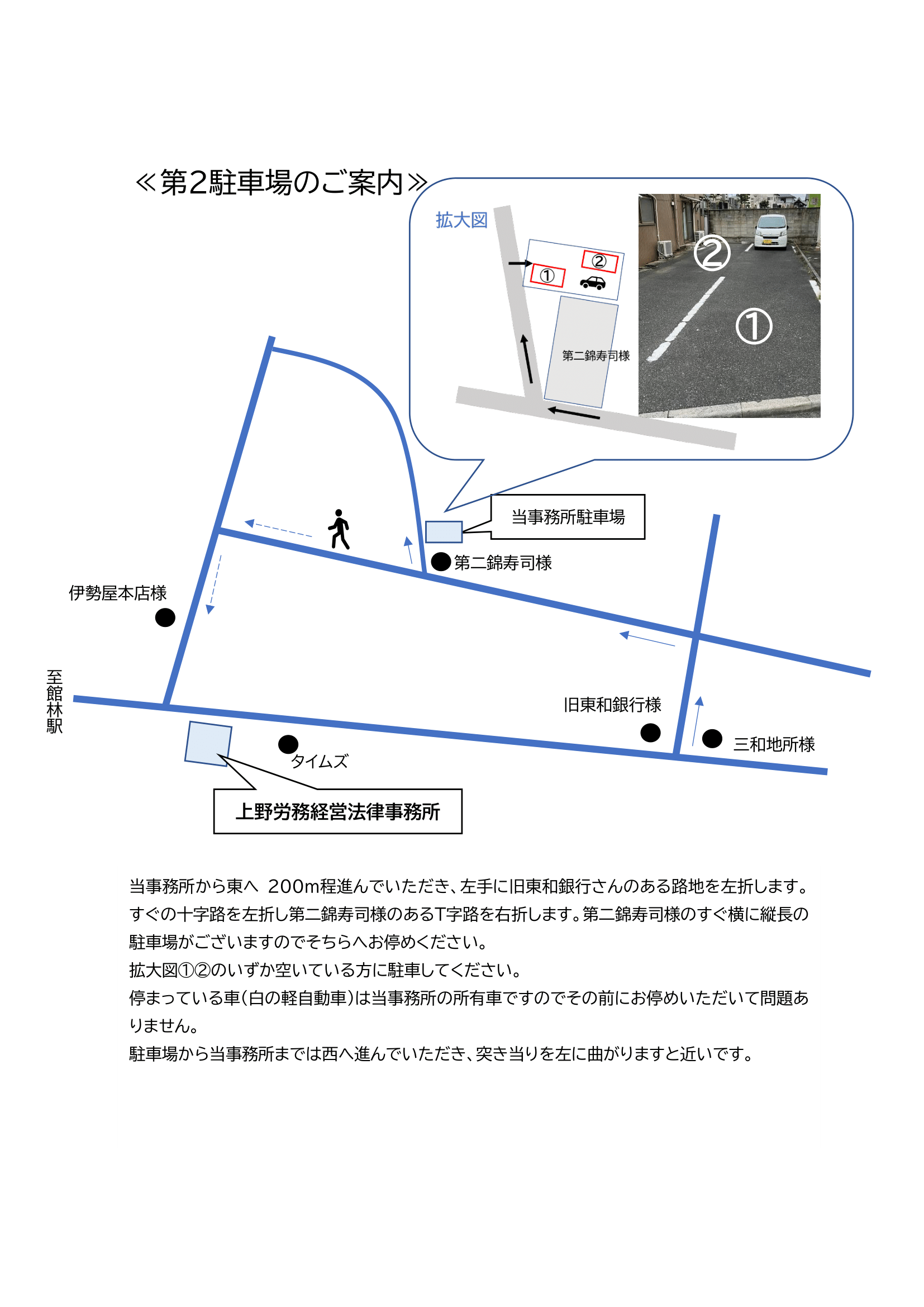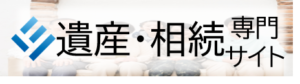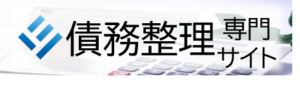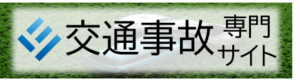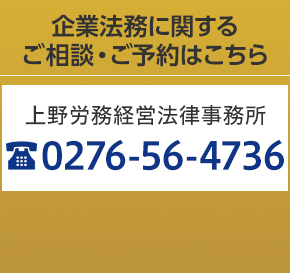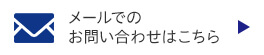固定残業代制度の見直しが「不利益変更」とされた裁判例
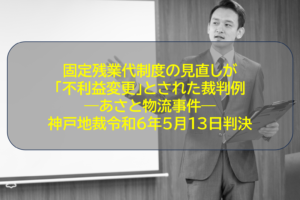
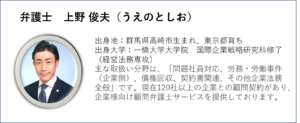
事案の概要
本件は、物流会社に勤務する運転手(原告)が、会社(被告)を相手取り、未払の割増賃金および労働基準法114条に基づく付加金の支払いを求めた事案です。
原告は長年、大型・牽引車の運転手として勤務しており、会社はもともと「歩合給」を賃金に組み込んでいました。しかし、旧制度では歩合給に時間外手当が含まれていたことが就業規則と矛盾し、法的問題があると指摘されました。
これを受けて会社は平成26年に賃金規定を改定し、歩合給を廃止して「運行時間外手当」という新たな手当を導入しました。これは運賃収入の一定割合(14~15%)などを基準に支給されるもので、名称上は時間外労働に対する手当とされていました。
この改定に際して会社は複数回の説明会を開催し、「迷惑料」として一時金を支給する代わりに合意書の取り交わしを求めました。
会社側は、改定後も総支給額は変わらず、固定残業代としての説明を行ったと主張しましたが、原告はこの改定が実質的に割増賃金を支払わない制度へのすり替えであると反発し、未払賃金と付加金を求めて提訴しました。
神戸地裁は一部原告の請求を認容し、会社に対し約250万円の支払いを命じる判決を下しました。
判例のポイント
本判決の要点は、①賃金規定の変更が労働者に対する不利益変更に該当するか、②「運行時間外手当」が割増賃金に充当できるか、③付加金の支払いが相当か、という3点に集約されます。
裁判所はまず、旧制度では歩合給が割増賃金の基礎に含まれる賃金として扱われていたにもかかわらず、新制度では「運行時間外手当」が時間外手当への充当を前提とするものに変更されており、労働者にとって不利益となる点を指摘しました。
これは、割増賃金の対象となる賃金が実質的に減少する効果を持つため、労働者にとっては著しい不利益となります。
また、会社は説明会などを通じて改定内容への「理解」を得たと主張しましたが、裁判所は「迷惑料の支払いと引き換えに改定を受け入れさせる手法」「改定による不利益性の矮小化」「割増賃金の支払い義務の誤解を招く説明」があったと認定し、自由意思に基づく合意とは認められないとしました。
さらに、運行時間外手当の中でも、運賃収入に比例する部分は旧歩合給と実質的に同じ性質であり、割増賃金の算定基礎に含めるべきであると判断しました。一方、これを割増賃金への「充当」とすることは認められず、会社には法定割増賃金を別途支払う義務があるとされました。
加えて、会社側の不適切な対応や説明不足も考慮し、労基法114条に基づく「付加金」の支払いも命じられました。裁判所は、単なる未払ではなく、企業側の制度設計・運用のあり方自体に問題があるとして、制裁的な意味合いを込めた判断を下したといえます。
まとめ
この判決は、固定残業代制度を採用・変更する企業にとって極めて重要な教訓を含んでいます。
制度変更によって賃金構造が実質的に労働者に不利益を与える場合、それがいかに丁寧に「説明」されたとしても、労働者の自由意思に基づく「同意」としては認められない可能性があることを示しています。
特に、本件のように名称や制度の表面を変えつつも、実態としては賃金構造を変更する場合、「理解」と「同意」の取得には慎重を期すべきです。説明会の開催やシミュレーション資料の提示は必要ですが、不利益性を適切に開示し、質問や懸念に真摯に対応することが不可欠です。
また、賃金のうち割増賃金に充当できる部分と、基礎賃金として扱うべき部分とを明確に分ける「判別性」が確保されていない場合、企業が想定していた「固定残業代」としての効果は無効となるリスクがあります。
さらに重要なのは、就業規則や賃金規定を変更する際、その合理性が問われるという点です。労働契約法第10条に基づき、不利益の程度、必要性、相当性、説明・交渉の経緯などが総合的に判断されるため、文書による合意書だけでは不十分です。
社労士先生や人事担当者様には、自社の就業規則や固定残業代制度が法的に有効な設計となっているか、定期的にチェックすることが求められます。制度変更を検討する際には、労働者の納得と法的リスクの両面に配慮した丁寧な運用が不可欠です。
弁護士の視点
歩合給により残業代を支払うという旧来の賃金規定は、かつては多くの企業で見られたものであり、いわゆる「○○方式」などと称して一部のコンサルタントが推奨したことで広まりました。
本件でも、会社はその旧規定が法的に問題があると判断し、是正のために4回にわたる説明会を実施し、賃金規定の改定を行っています。運用面では丁寧かつ慎重に進められていたと評価できる対応です。
しかしながら、裁判所はこの賃金改定を「労働者に対する不利益変更」であるとして無効と判断しました。その理由は、説明会等において旧規定が違法であったことや、その違法性によって改定の必要性があったことを会社が十分に説明していなかった点にあります。
結果として、使用者側にはかなり厳しい判断が下された形ですが、現行の判例理論──特に不利益変更における「合理性の判断基準」──を踏まえると、この結論はやむを得ないものと感じられます。