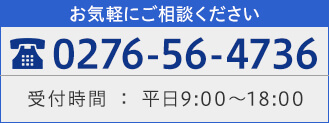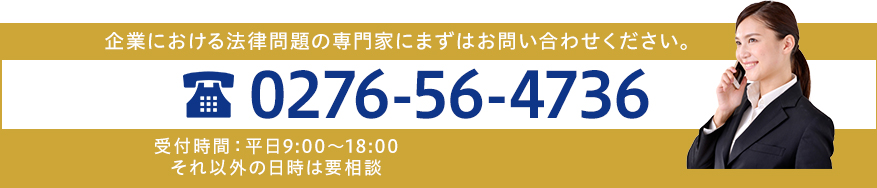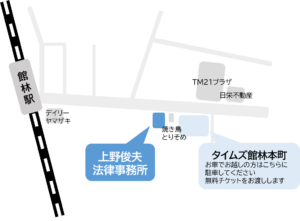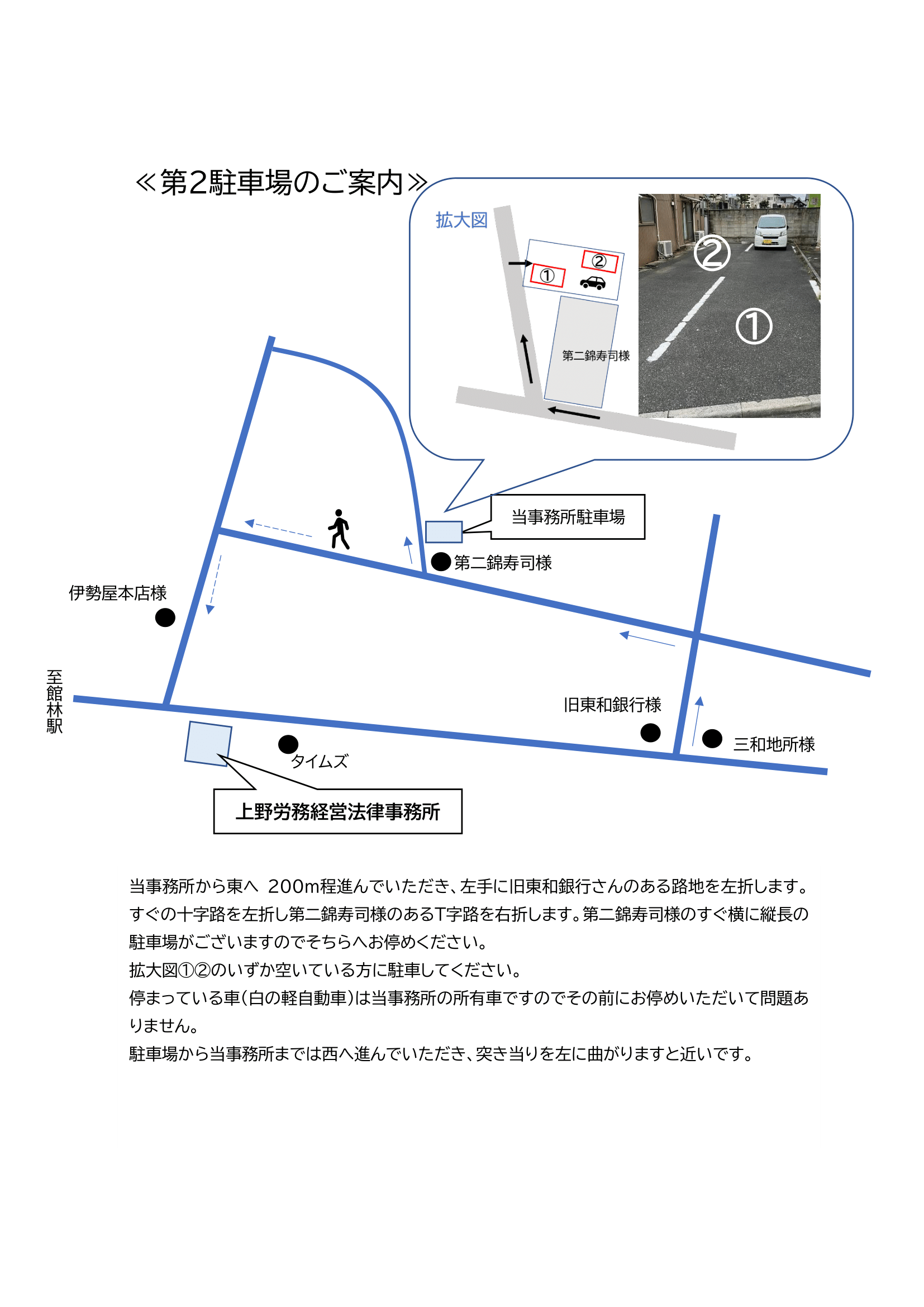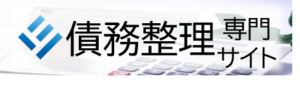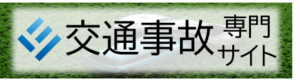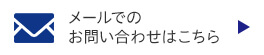問題社員対応1【問題社員とは】
問題社員には、大きく2つのタイプがあります。
1つめは、「非協調型」といって、業務命令を聞かない、自己中心的な言動に終始する、営業に出ているがきちんと仕事をしているのか不明等のタイプの社員です。
2つめは、「能力不足型」といって、仕事のパフォーマンスが異様に低いタイプの社員です。
また、上記2つのタイプ以外にも、違法行為をする社員も問題社員に含まれます。
上記のような問題社員の存在は、職場の雰囲気を悪くしたり、またそれによって優秀な社員が辞めてしまったり等、会社にとって負の影響があるでしょう。
昨今の人手不足の現状では、いかにして社員を辞めさせないようにするかが、会社の経営陣・管理職・総務の重要な職務と言えます。
ところで、何故社員は辞めていくのでしょうか。
ここで、リクナビが転職経験者100人に調査した退職理由の本音ランキングをご覧ください。
| 1位 上司・経営者の仕事の仕方が気に入らなかった 23% |
| 2位 労働時間・環境が不満だった 14% |
| 3位 同僚・先輩・後輩とうまくいかなかった 13% |
| 4位 給与が低かった 12% |
| 5位 仕事内容が面白くなかった 9% |
| 6位 社長がワンマンだった 7% |
| 7位 社風が合わなかった 6% |
| 7位 会社の経営方針・経営状況が変化した 6% |
| 7位 キャリアアップしたかった 6% |
| 10位 昇進・評価が不満だった 4% |
退職理由ランキング(リクナビNEXT:『退職理由の本音ランキング』)
このランキングを見ると、
1位に「上司・経営者の仕事の仕方が気に入らなかった」(23%)、
2位に「労働時間・環境が不満だった」(14%)、
3位に「同僚・先輩・後輩とうまくいかなかった」(13%)、
と様々な理由が挙げられています。1位と3位の理由は人間関係の不満によるもので、回答者のうち実に約4割が人間関係の不満から退職を決行したことが窺えます。
問題社員の存在は人間関係の不満につながりますから、問題社員の存在は他の社員の退職理由になり得ます。
このようなことからすれば、問題社員対応は、会社からの人材流出や人手不足を食い止めるという点で極めて重要です。
では、どのように問題社員に対応していけばいいでしょうか。
問題社員がいた場合、単純に解雇してしまえば話は早いように感じますが、実は、問題社員といえど、裁判所はそう簡単に解雇を有効と判断しません。
解雇の有効性が裁判で争われた場合、解雇は無効とされることが多く、解雇は原則として無効とも言いえます。
非協調型、能力不足型だけではなく、パワハラをしていた場合であったり、業務とは関係のない刑事事件(飲酒、痴漢など)を起こした場合であったりしても、いきなり解雇するのは難しく、裁判で会社側が負ける可能性が高いです。
もちろん解雇は就業規則に則ってされるわけですが、就業規則に則って解雇したとしても、容易に有効とはなりません。
例えば、「会社に無断で5日連続欠勤した場合、会社は社員を普通解雇する」という就業規則があった上で、5日間無断欠席した社員がいたとします。
この場合、この社員を解雇することに問題はないように思われますが、裁判になった際には、解雇権の濫用と見なされ解雇が無効になることがしばしばあります。
ここで、高知放送事件の例を見てみましょう。
|
高知放送のアナウンサーXが、午前6時からの10分間のラジオニュースについて、2週間に2回の寝過ごしによる放送事故を起こした 第1事故は、宿直勤務後、6時20分まで寝てしまい、全く放送ができなかった 第2事故は、寝過ごしで、5分間ニュースを放送できなかった 会社から、事故報告書を求められ、事実と異なる報告をした そこで、会社は、普通解雇した 解雇の有効性が争われた |
(最高裁 S52.1.31)
問題社員の典型例ともいいうるこの事件について、裁判所は最終的に、解雇は無効であるとの判断を下しました。
裁判所が解雇無効であると判断した理由としては、以下のようなものでした。
- アナウンサーXの寝過ごしは故意ではない
- 放送時間の空白は少ない
- 会社としてアナウンサーXの寝過ごしを防ぐべき万全の措置をしていない
- アナウンサーXの普段の勤務態度は悪くない
- 過去に、会社で放送事故を起こしたという理由で解雇された者はいない
このように、裁判実務上、解雇は原則として無効であり、例外的に有効として運用されているのが実情です。
そうは言ってもうちは解雇無効の裁判なんて起こされることはない、と思っていらっしゃる経営者の方も多いと思われます。
この点、どのように裁判に発展していくかというと、まず、解雇された社員は、解雇後「なんとか会社に復讐してやりたい」、とインターネットで情報を集めます。
すると、「解雇は無効だ」というようなことが書いてある弁護士のホームページに辿り着きます。
社員がその弁護士に相談に行くと、弁護士から「解雇は無効になるから、裁判を起こせば、裁判をやっている期間の給料を支払ってもらえる」という説明を受けるでしょう。
(弁護士費用は、着手金と報酬金で成り立っていますが、
解雇無効の裁判は着手金なしで依頼を受けることもあるくらい、労働者側が圧倒的に有利な裁判です!)
そして、ある日突然「解雇は無効だ、速やかに復職させろ」という内証証明郵便が届くのです……。
それでは、解雇が無効とされた場合の法的処理はどのように進むのでしょうか。
裁判をやっている期間、労務の提供はない(会社に来ない)にもかかわらず、裁判をしていた期間の給料の支払い義務は発生し続けます。
これを、バックペイと言います。
例えば、解雇無効を争う裁判を3年間行った場合、年収400万円の労働者ならば1200万円の給与相当分(バックペイ)を支払うリスクが生じます。
実際の裁判では、判決ではなく和解で終わることも多いですが、和解に当たってはバックペイが発生していることを踏まえて解決金が定められることが多いですので、結果として高額の解決金を支払わざるを得ないのが実情です。
ですので、たとえ問題社員であっても、安易に解雇をすると、後で裁判を起こされた場合に無効となると思っていただいた方がよいです。
東芝事件では、解雇された年収568万円の社員が12年裁判をした結果、最終的に会社は6000万円をバックペイとして支払うことになりました。
このように解雇が無効とされた場合、会社は多額の金員を支払う羽目になり、大きな打撃を受けることになるのです。
今回のコラムでは、問題社員であっても基本的に解雇は難しく、かつそれに伴う会社側のリスクをお伝えしました。
次回は、解雇が難しい問題社員のパターンを中心に具体的にご紹介したいと思います。