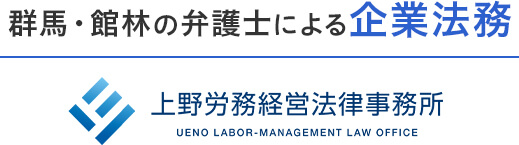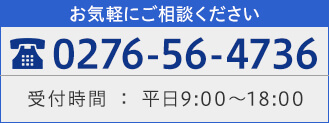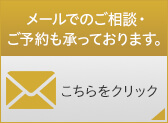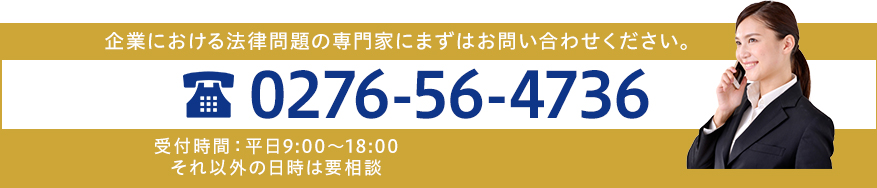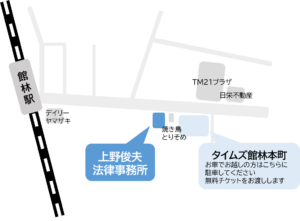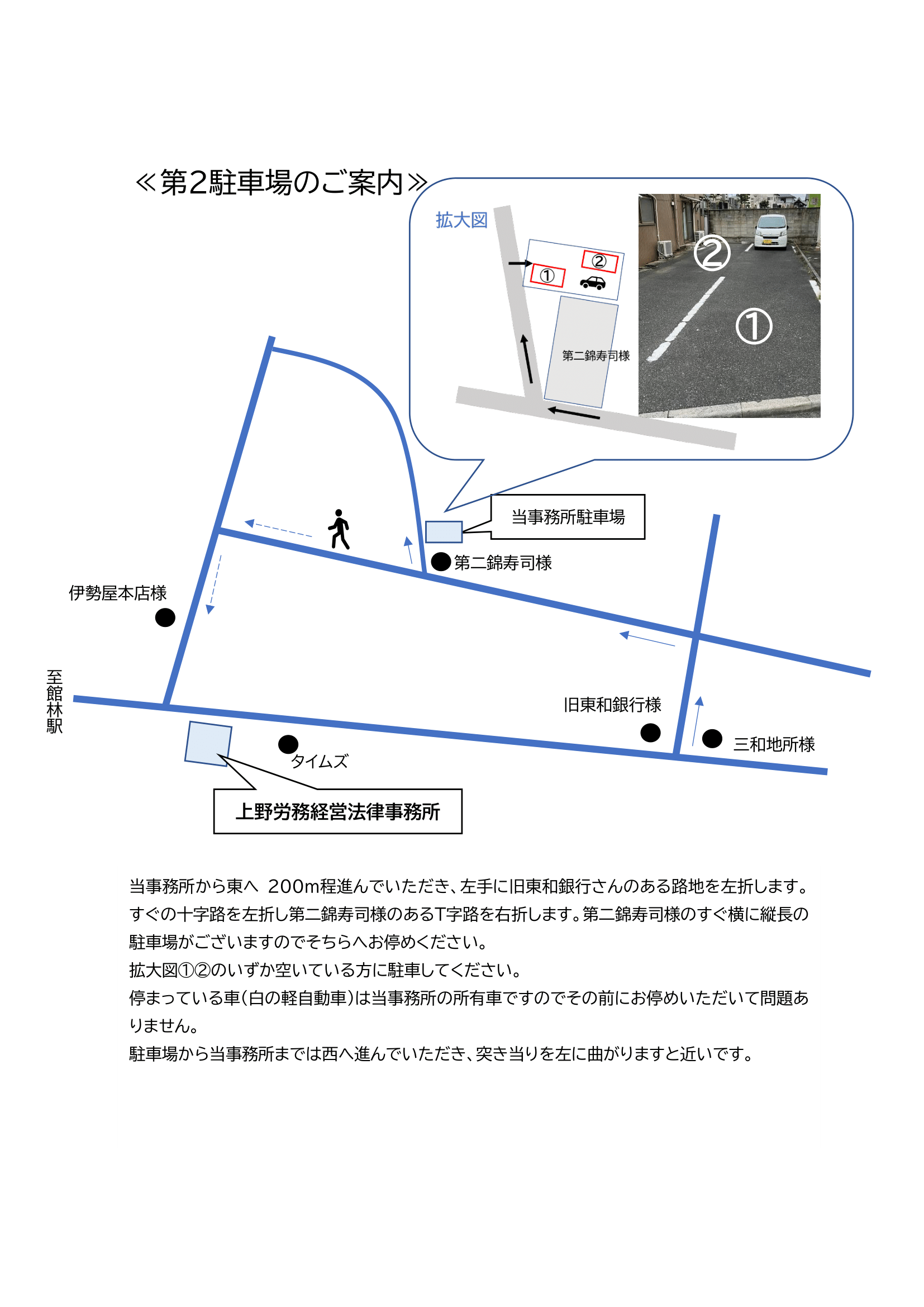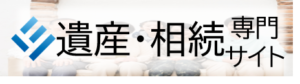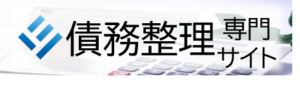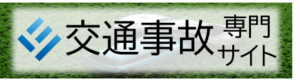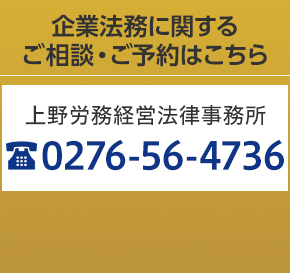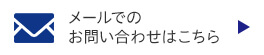問題社員対応の極意―懲戒処分

文書による業務指導を行っても問題社員の行動が改まらない場合には、懲戒処分を行いましょう。
懲戒処分を行う際のポイントは以下の通りです。
- 軽すぎず、重すぎずの処分を行う
- 公平性を保つ
- 告知聴聞手続きをする→手続きを行ったことを書面で残す
- どのような不当行為があり、就業規則の何条に違反するのか懲戒処分通知書に記す
この公平性については、過去社内であった処分事例と比べて公平か、他の従業員と比べて公平か、という2つの視点から考えましょう。
懲戒処分を行うのは、自身の行為が違法なことだということを問題社員に分かってもらうためです。
違法行為があったということをきちんと文書に残し、問題社員の行動を明らかにするようにしましょう。
まずはけん責から
懲戒処分は、以下のように軽いものから重いものまで、6つの処分に分かれています。
以前こちらのコラムで解説したように、原則、解雇はできません。
そのため、懲戒処分を行う際も諭旨解雇や懲戒解雇は基本的に行わないようにしましょう。
諭旨解雇であっても、裁判所は解雇と同視する傾向にあります。
また、処分が重くなるほど裁判では無効とされやすくなります。
そこで、まずはけん責から処分を行うようにしましょう。
けん責とは、労働者を戒めて始末書を提出させる処分のことを指します。
労働者の問題行動が発覚した場合には、書面を残すという意味からも、戒告からではなく、けん責から処分を行いましょう。
懲戒処分の運用法
懲戒処分の規定を設けてはいるが、あまり活用していない、という会社も多いのではないでしょうか。
懲戒処分とは、会社の秩序維持のために法律で認められている非常に効果的な制度です。
せっかく規定があっても運用できていないのでは、まさに宝の持ち腐れです。
労働者の問題行動が明らかになると、ついつい「解雇だ!」と頭に血が上ってしまいがちですが、これは非常にもったいないことです。
まずはけん責の処分を行い、それでも問題行動が改まらなければより重い処分を行うようにしましょう。
それでも改まらなければまた次・・・と、軽い処分から重い処分へ、懲戒処分を重ねていくようにしましょう。
何度も処分を重ねても問題行動が改まらないようであれば、解雇が有効となる可能性も出てきます。
しかし、解雇の前にまだするべきことがあります。
次のステップは次回解説いたします。