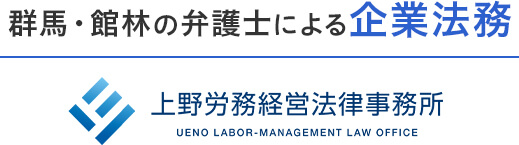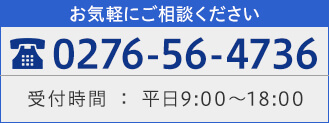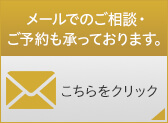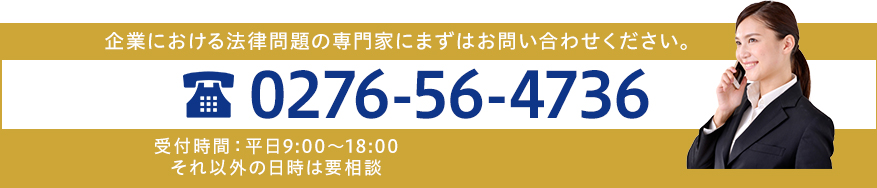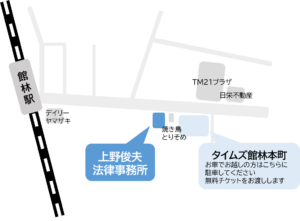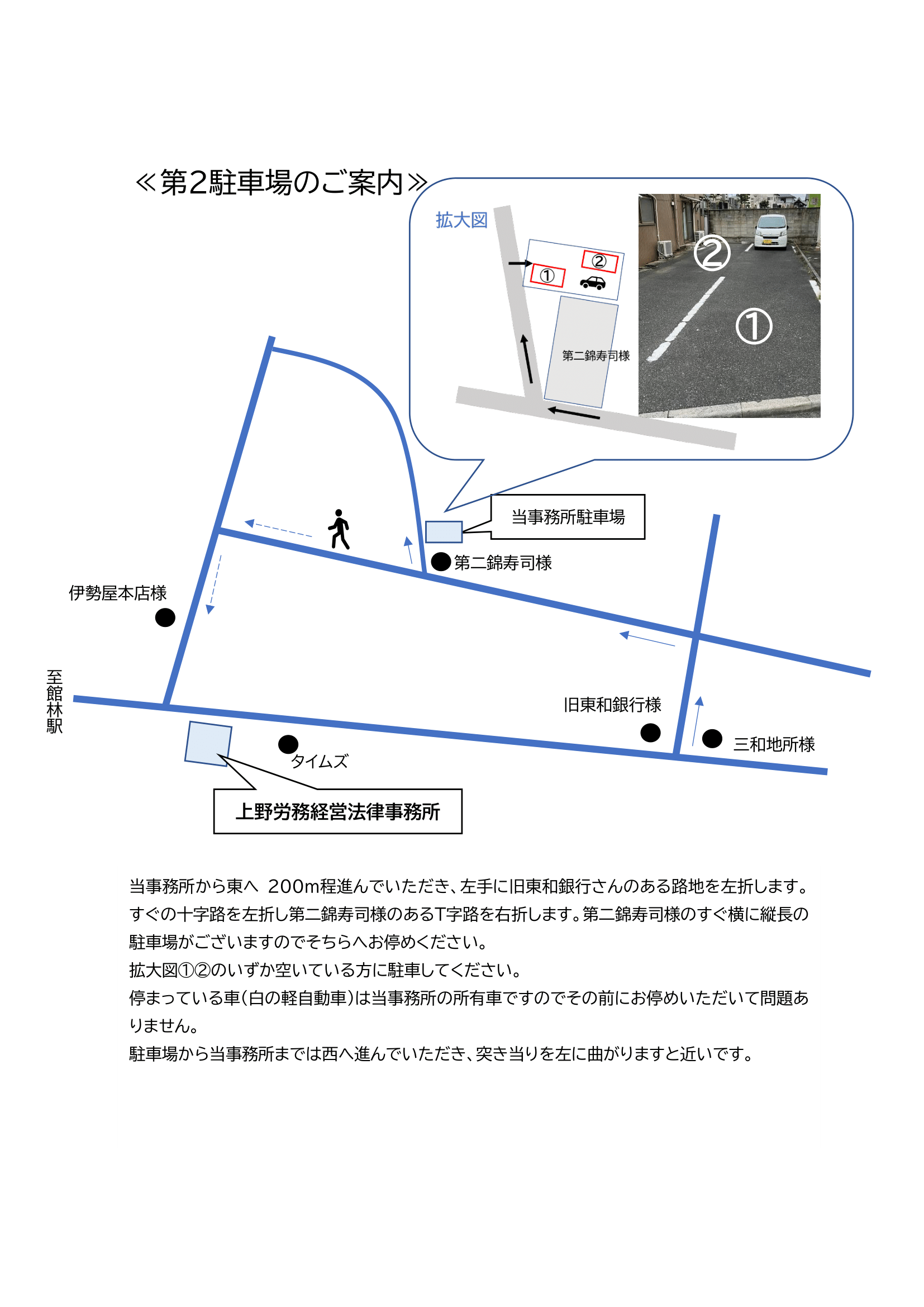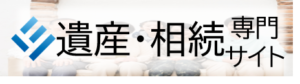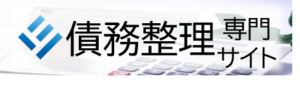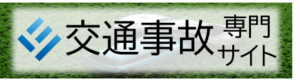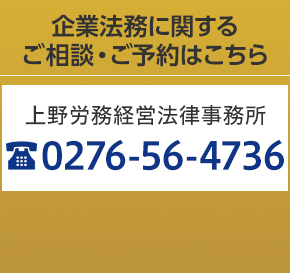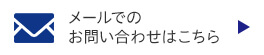Vol.11【中小企業のための時効の知識 その1】
(平成28年4月13日)
【中小企業のための時効の知識 その1】
「時効」というと,皆様は何を思い浮かべますか?
私は,法律の勉強をする前は,時効と言えば,もっぱら刑事事件でのイメージでした。
犯罪を犯しても,一定期間を経過すると,罰することができないというものです。
ドラマなどで,時効寸前に,刑事と犯人がせめぎ合いをして,最終的には逮捕されるなどのシーンを度々見て,このような印象を持ったのだと思います。
時効は,刑事事件,民事事件の両方であります。
先ほどの話は刑事事件の時効ですが,弁護士になってからは,刑事事件の時効が問題となるようなケースにはほとんどぶつかっていません(時効になる事件は,被疑者いわば犯人が訴えられることはないので,弁護士は余程のことがない限り,刑事事件の時効には関係しないのです。)。
私が関与した事件で,時効が問題となったほとんどのものは,民事事件です。
特に,①中小企業の売掛金の時効,②交通事故の損害賠償請求権の時効,の二つが問題となります。
どちらも,消滅時効と言われるもので,①中小企業の売掛金は支払時期から5年(例外があります),②交通事故の賠償請求権は事故から3年で消滅します。
法律家ではない方で,誤解が多いのは,時効を止める方法です。
例えば,5年の時効であっても,請求書を送り続けていれば,時効を止められると思っている方をよくお見受けしますが,請求書を送るだけでは時効は止められません。請求書を送っていても5年経ってしまえばアウトです。
確実に時効を止めるためには,①債権を認めるという書面を貰う,②裁判を起こす,などのことが必要です。
やりやすいのは①です。
例えば,銀行は時効間際になると,融資先を訪問して,「承諾書」への署名を求めます。この行為の意味は,①の債権を認めるという書面を貰って,時効を止めることにあります。
そうだとすると,「自社の持っている債権が時効にならないように承諾書を貰いたいが,どのような書式にすれば良いか。」,という質問が生まれると思います。
次回のメールマガジンでは,どのような書面を貰い,時効を止めるかをお話しします。
- メールマガジンvol.101 「嘘ハラ」と思われる事案でハラスメント調査は必要か?
- メールマガジンvol.100 【抗うつ剤の服薬の虚偽告知が解雇事由として考慮されるべきとされた裁判例】
- メールマガジンvol.99 【セクハラ事案で「同意の抗弁」は通用するか?】
- メールマガジンvol.98【カスタマーハラスメントへの対応】
- メールマガジンvol.97【取締役会による退職慰労金減額の有効性】
- メールマガジンvol.96【カスタマーハラスメントの防止対策】
- メールマガジンvol.95【大谷選手と水原氏の件から考える不正領得への対策方法について解説】
- メールマガジンvol.94【大谷選手と松本氏の件から考える危機管理の初動の大切さについて解説】
- メールマガジンvol.93【松本人志氏対週刊文春の訴訟について解説】
- メールマガジンvol.92【偽装業務委託契約のリスクについて解説】