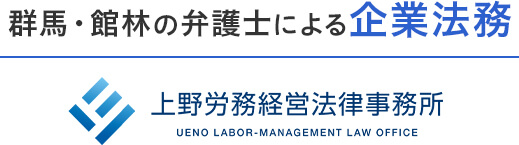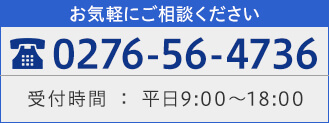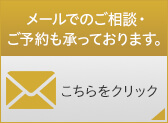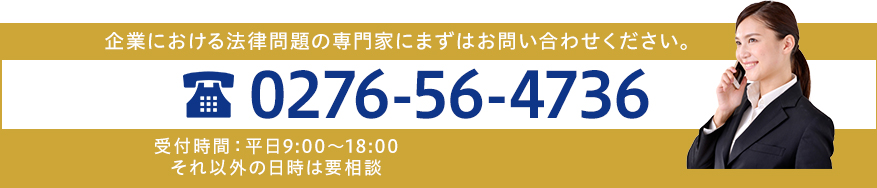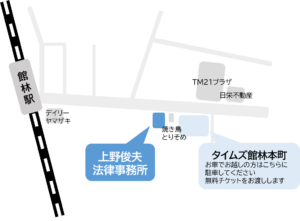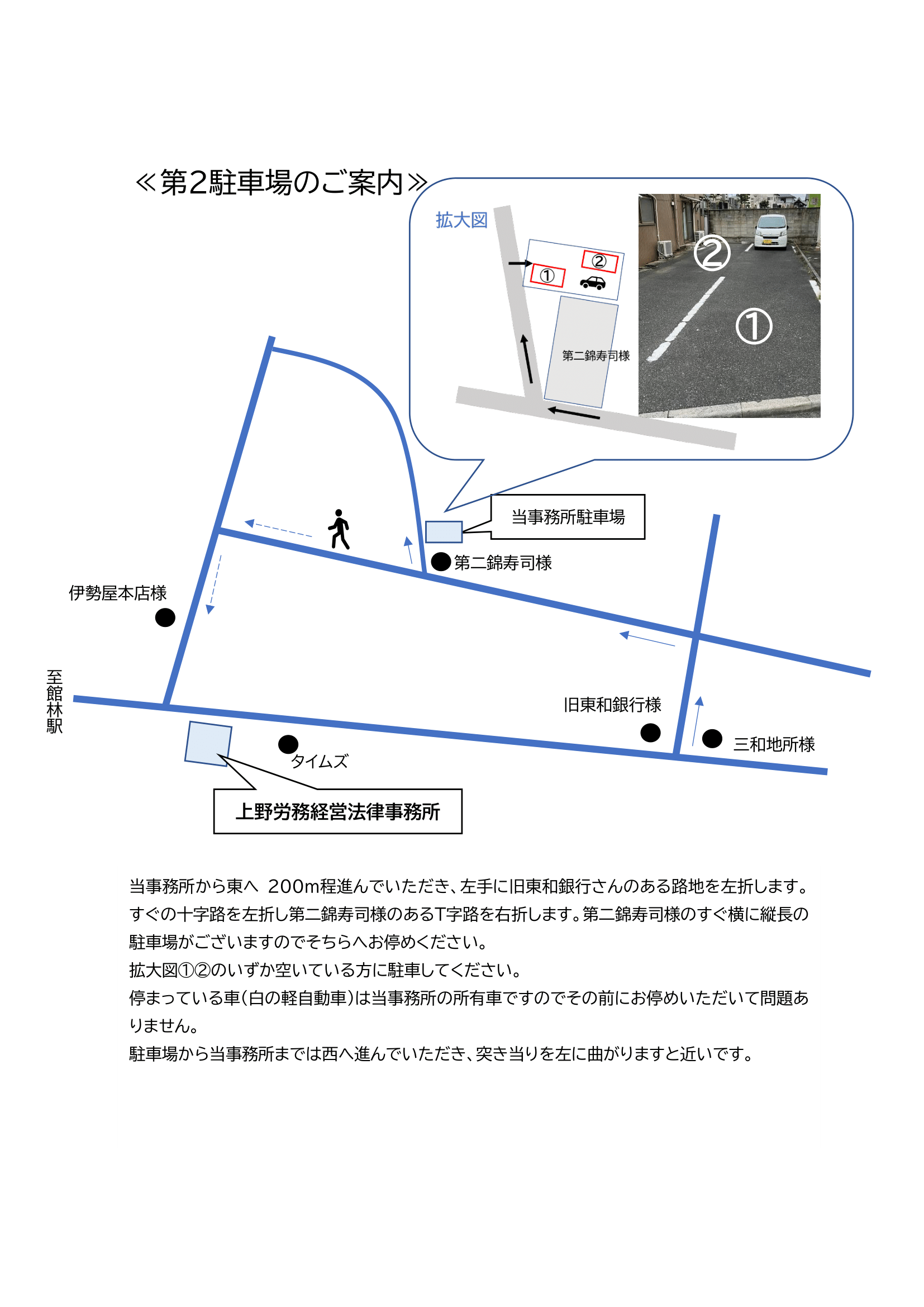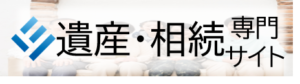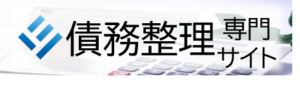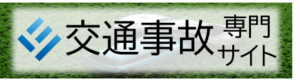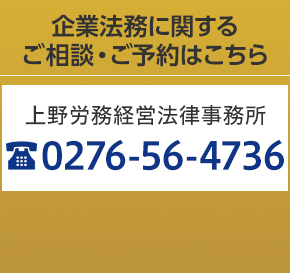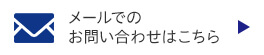Vol.26【中小企業のための解雇の知識について その6】
(平成30年3月30日)
【中小企業のための解雇の知識について その6】
前回のメールマガジンでは,解雇をするためには,懲戒処分を積み重ねることが必要と述べました。
今回は,処分を重ねるということの意味についてもう少し詳しくお伝えしたいと思います。
事業者さんの多くは,一度の問題行為(例えば飲酒運転)などで解雇しようとしたり,実際に解雇したりします。
しかし,このような解雇は余程の事情(例えば飲酒運転であれば自動車メーカーであるなど)がなければ,後で裁判を起こされると無効となってしまいます。
これは,法律で,解雇はよほどのことがない限りできない,と規定されているからです。
例外的にできるのは,誤解を恐れずに言えば,次の2パターンです。
一つ目は,例えば強盗などの凶悪犯罪,横領など会社の金銭に手を付ける犯罪をした時などです。
二つ目は,一つ目ほどの悪性な行為でなくても,処分が重ねてされたときです。
例えば,学生の退学処分を考えてみてください。何度も遅刻や無断欠席を繰り返す学生がいるとします。
常識的には,最初は注意をしたり,謹慎をさせたりします。いきなり退学にはしません。
この学校の例で言えば,謹慎などの処分をしても,生活態度が改まらない場合に,次に停学などの処分にするでしょう。
さらに,それでも素行が良くならず,無断欠席などを続けた場合に初めて退学ということになります。
このように,何度か更生の機会を与えたのに,それでも生活態度が改まらなかった上での退学処分であれば,親としても仕方がないと思うでしょうし,第三者が見てもやむを得ないと思うところです。
退学という処分が子供に与えるインパクトは大きいので,何度か更生の機会を与えてはじめて,退学処分が正当化されます。
解雇も,社員は生活の糧を失うことになるので,社員への影響は大きいです。
解雇は,退学と同様一つの共同体から強制的に退出させるもので,処分を受けた方からすると大きなインパクトがあります。
ですので,ある程度更生の機会を与えたということの上での処分でないと,裁判所からは不当解雇で無効という認定を受けてしまうのです。
有効に解雇するには,何度か処分を繰り返すというプロセスが必要になってくるので,この点については十分に注意してください。
- メールマガジンvol.101 「嘘ハラ」と思われる事案でハラスメント調査は必要か?
- メールマガジンvol.100 【抗うつ剤の服薬の虚偽告知が解雇事由として考慮されるべきとされた裁判例】
- メールマガジンvol.99 【セクハラ事案で「同意の抗弁」は通用するか?】
- メールマガジンvol.98【カスタマーハラスメントへの対応】
- メールマガジンvol.97【取締役会による退職慰労金減額の有効性】
- メールマガジンvol.96【カスタマーハラスメントの防止対策】
- メールマガジンvol.95【大谷選手と水原氏の件から考える不正領得への対策方法について解説】
- メールマガジンvol.94【大谷選手と松本氏の件から考える危機管理の初動の大切さについて解説】
- メールマガジンvol.93【松本人志氏対週刊文春の訴訟について解説】
- メールマガジンvol.92【偽装業務委託契約のリスクについて解説】