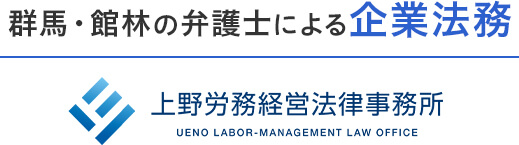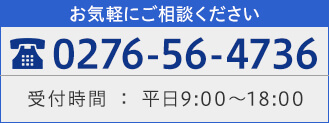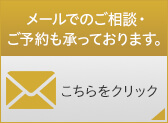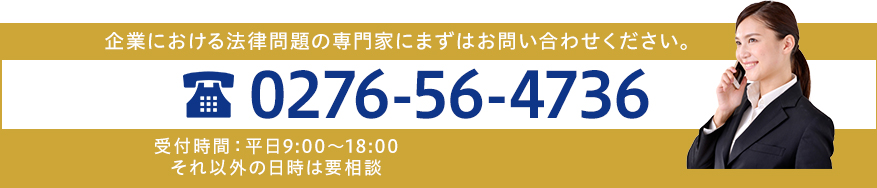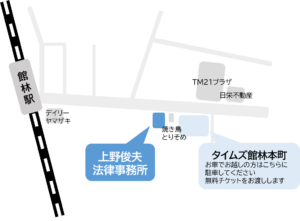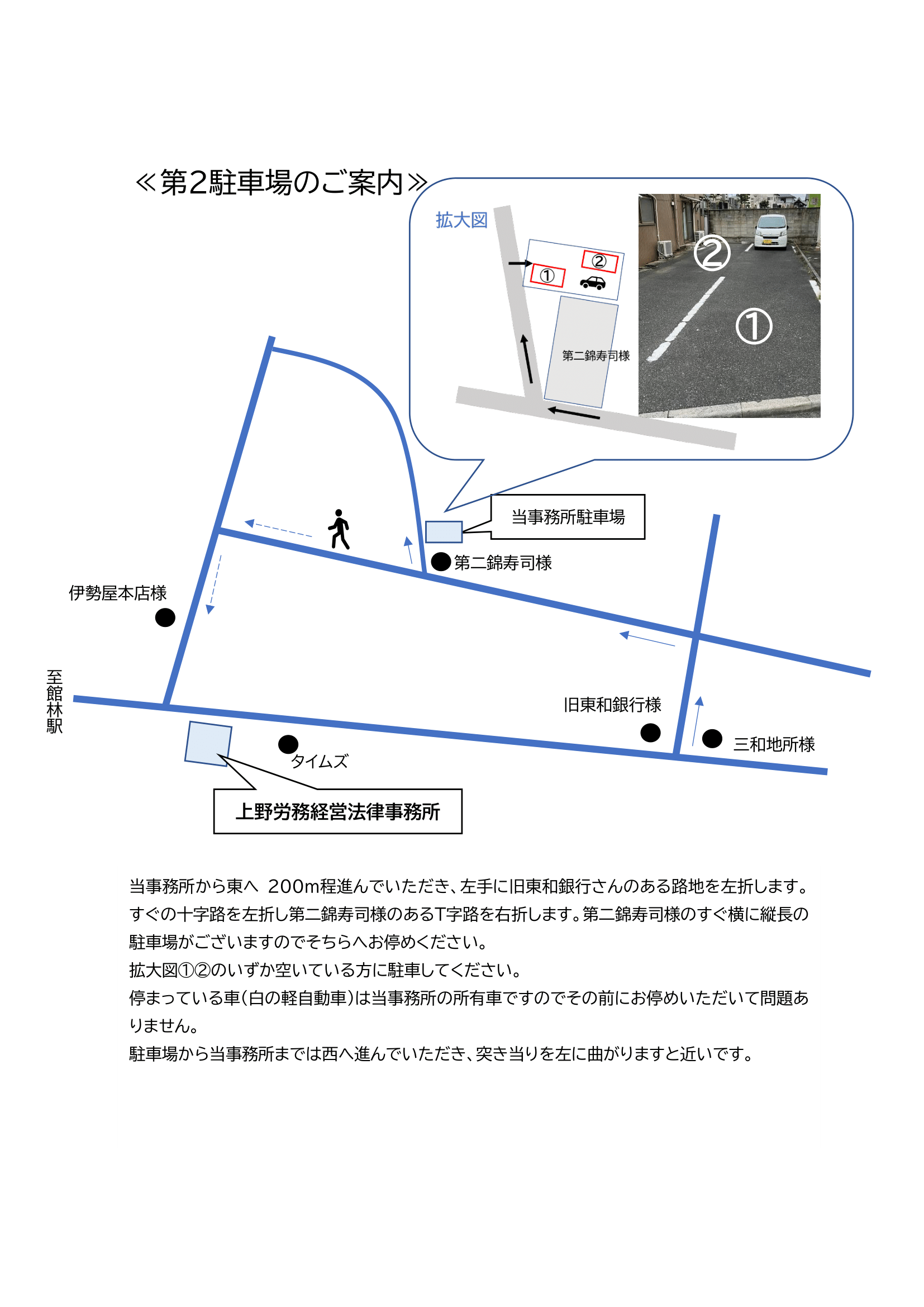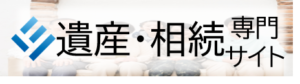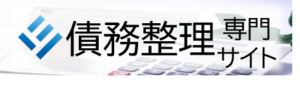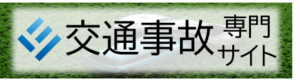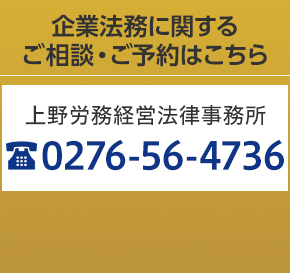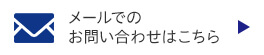Vol.62【賃金引下げについての法律問題 その2】
【賃金引下げについての法律問題 その2】
前回のメールマガジンで、中小企業において、どのような時に給料の引き下げができるかを説明しました。
考えられるのは以下の3パターンです。
1. 給料引き下げについて社員に同意してもらう
2. 役員を降格させて役職手当を減額する
3. 資格等級制度の給料体系をとっている場合に資格等級を下げる
1については、中小企業の実務ではよく利用されているということ、また、社員が不本意にではなく本心から同意したと言えない場合、給与引き下げの同意は無効になる可能性が高いということ等についてお伝えしました。
今回は、
2. 役員を降格させて役職手当を減額する
3. 資格等級制度の給料体系をとっている場合には資格等級を下げる
について、ご説明いたします。
まず、2の役員を降格させて役職手当を減額するという対応についてです。
これは例えば、課長補佐に対して役職手当を3万円支払っていたところ、この課長補佐の勤務態度や業績に問題があるとして、役職を解くと共に役職手当の支払いを停止するようなケースです。
このケースでは、役職を解くことに伴って手当がなくなり、受け取る給与も減ることになるわけです。
この降格は会社の人事権の行使といえます。
裁判所は、会社の人事権の行使について、会社側に大きな裁量を認めており、よほど濫用的な人事権の行使でない限り適法と判断する傾向があります。
従って、上記のようなケースで役職を解くことと、役職手当が不支給になることに伴う総支給額の減額は、適法となる可能性が高いです。
次に、3の資格等級制度の給料体系をとっている場合に資格等級を下げるという対応についてです。資格等級制度というのは、例えば、3等級の社員の基本給は15号俸の30万円、7等級の社員は26号俸の24万円と定められているなど、等級と基本給などが連動している給与形態です。
このケースで、働きぶりが悪いとして3等級から7等級に降格されると、基本給が15号俸の30万円から26号俸の24万円に減ることになります。
このような降格は、就業規則の根拠か、社員の同意があればできます。
ただ、日本では、基本給は基本的には下げないという雇用の考え方が浸透しているので、裁判所は、資格等級制度による降格は役職手当の減額に比べ、厳しく判断する傾向があると感じます。よほど能力が欠けているとか、転職が広く行われる業界であるとかなどの事情がない限り、等級を下げることによる減給は無効になるリスクが高いです。
従って、資格等級の引き下げによる給与の減額は、慎重に行っていく必要があります。具体的には、何か問題行動があった場合にいきなり等級を下げるのではなく、厳重注意などの文書での処分をして、それでも改まらない場合に等級の引き下げを行うようにしたほうが良いです。
- メールマガジンvol.101 「嘘ハラ」と思われる事案でハラスメント調査は必要か?
- メールマガジンvol.100 【抗うつ剤の服薬の虚偽告知が解雇事由として考慮されるべきとされた裁判例】
- メールマガジンvol.99 【セクハラ事案で「同意の抗弁」は通用するか?】
- メールマガジンvol.98【カスタマーハラスメントへの対応】
- メールマガジンvol.97【取締役会による退職慰労金減額の有効性】
- メールマガジンvol.96【カスタマーハラスメントの防止対策】
- メールマガジンvol.95【大谷選手と水原氏の件から考える不正領得への対策方法について解説】
- メールマガジンvol.94【大谷選手と松本氏の件から考える危機管理の初動の大切さについて解説】
- メールマガジンvol.93【松本人志氏対週刊文春の訴訟について解説】
- メールマガジンvol.92【偽装業務委託契約のリスクについて解説】